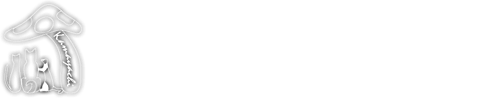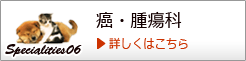皮膚科
皮膚はからだの中で最も大きな器官であると同時に、体温の調整、水分の保持、外部刺激からのバリア機能、免疫監視機構、知覚、ビタミンD合成などの数多くの機能を有しています。症状として痒がる、皮膚が赤い、フケが多いといったことは飼い主様にもすぐわかる症状であるため、動物病院において一番来院数が多い診療科目です。
当院では治療に入る前にしっかりと皮膚病の発生状況を把握したうえで、身体検査はもちろん、皮膚掻把検査、被毛・毛根検査、細胞診、真菌検査、細菌の培養同定、抗菌薬の感受性検査を行い、原因の特定、治療を行っております。皮膚病の種類によっては、血液検査、ホルモン検査、皮膚病理検査をおこなってはじめて特定に至る皮膚病もあります。
以下に代表的な皮膚科疾患を示します。
膿皮症
膿皮症とは、主に毛穴を中心に細菌が増殖し炎症を起こす皮膚病です。犬ではヒト、ネコに比べ、細菌性皮膚疾患の発症率が高いことが知られています。
主に原因となる細菌はブドウ球菌といわれる細菌で、本来は病原性が強い細菌ではないが、アトピー性皮膚炎などで皮膚バリアー機構が弱っていると膿皮症が発生しやすくなるといわれている。そのため根本にある疾患の管理をすることが重要となる。
治療は、抗生剤の投与および抗菌性のシャンプーによる薬浴、根本疾患の管理が必要である。
どういったタイプの犬種にもみられるが、短毛種では毛穴を中心とした小さな盛り上がり(丘疹)を形成し、脱毛を伴うことも多い。(触るとぶつぶつしたものが皮膚で触れる)
 短毛種にみられる膿皮症 |
長毛種ではどちらかというと背中側に多く発生し、ふけを伴い、束となって環状に脱毛(表皮小環)する場合が多い。
 長毛種にみられる膿皮症 |
 表皮小環 |
脂漏性皮膚炎
脂漏性皮膚炎とは、簡単にいうと体表の皮脂が過剰となるために発症する皮膚炎である。皮脂による体臭が強くベタつくタイプと、フケが過剰になるタイプが存在する。また、二次的にマラセチア性皮膚炎や膿皮症を起こすことがある。
治療は脱脂シャンプーまたは角質溶解性シャンプーによるスキンケアを中心に、症状により抗生剤、抗マラセチア剤、痒みが強い場合には一時的にステロイドを使用することもあるが、治療は生涯にわたることが多い。
また、当院において重症症例に対し免疫抑制剤の一つであるシクロスポリンの投与により著効を示した例を複数経験している。

|

|
|
| 生後2か月ごろより、首回りのみの脂漏症をみとめ、痒みのあるときのみ投薬をしていたシーズー。5歳時に突然全身へ脂漏がひろがり、シャンプー週2回、皮膚保湿剤、抗生剤、抗マラセチア剤投与、ステロイド投与を1か月間継続するも皮膚の痒み、ベタつき、脱毛に顕著な改善がみられなかった症例。シクロスポリン投与前 | ||

|

|
|
|
抗生剤、抗マラセチア剤の休薬、ステロイド剤の減量をし、 シクロスポリン追加投与後1か月。痒み、赤みが減少し、発毛が見られる。 |
||

|

|
|
| 投与後2か月。痒みはまだある程度残るものの、かなり発毛が進む。 | ||
食物誘発性アレルギー性皮膚炎
犬の皮膚におけるアレルギー反応のうち最大25%が食物に関係していると考えられている。思っていたより少ないと感じませんか?自分の経験では実際さらに少ないのではないかと思っている。食物誘発性アレルギー単独による皮膚トラブルとなると数%しかいないのでないでしょうか。しかし、皮膚に痒みのトラブルがみられると食事が悪いのかもしれないとペットショップで低アレルギーフード(?)、自然派フード(?)といわれるドッグフードを購入し、試された経験がある飼い主様は非常に多いと思います。そして、痒みに変化がないと落胆された経験のある飼い主様もまた同じくらいいらっしゃるのではないでしょうか。血液検査等による動物アレルギー検査も存在するが、実際、確定診断を下すことは非常に困難であり、大部分の症例は、疑いありの診断にとどまるケースがほとんどである。
唯一の確実な方法は、特定の食品摂取と一連の臨床徴候の発現の間に関連性をみとめ、さらに原因となる食品を除去後症状の軽減、および再摂取した時に症状が再発されることを確認することである。(除去食試験・再負荷試験)
食事の変更により、皮膚の諸症状に軽快がみられた症例をご紹介します。

|
食事変更前 | |
|
ステロイド等の治療に反応がほとんどなく、全身にかなりの痒みがみられた犬の腹部 診察室内でもしきりに体をかきむしっていた |
||

|
食事変更2週間 | |

|
食事変更1か月 | |
|
腹部の色素沈着がかなり改善し、炎症が落ち着いてきていることがわかる このころには、診察室内でもかくしぐさは一切みられなくなった。 |
||

|

|
食事変更前 | |
|
ステロイド等の治療に反応の弱く、季節性がみられない全身の痒みがあった犬 下腹部の色素沈着と前肢肢端尾側の脱毛がみられる。 |
|||

|

|
食事変更2週間 | |
| 腹部の色素沈着が減少 | |||

|

|
食事変更1か月 | |
| 腹部および前肢の発毛もみられる | |||
皮膚糸状菌症
皮膚糸状菌症とは、いわゆる真菌(カビ)による人獣共通感染症である。症状としては円形の脱毛があり、紅班(赤み)、落屑(フケ)などを伴い、時に脱毛部の色素沈着(シミ)を認める。主に、子猫、子犬での発症が多いが、免疫不全動物(高齢や腫瘍など)においても発症がみとめられる。主な原因菌として3種類報告があるが、それぞれ感染源と考えられるものが異なるため、今後の治療、再発防止を考えると菌の特定が必要と思われる。
治療は、抗真菌剤の内服、外用塗布に加え、抗真菌シャンプーでの薬浴も効果がある。
一方で、動物自体の免疫状態に加え、環境が汚染されてしまうことによって完治に導くのに非常に時間を要することと、再発が非常に多い疾患である。そのため、感染源をできるだけ特定し、可能な限り排除することが重要であり、徹底した環境の清浄化に努める必要がある。

|

|
|
|
感染のみられる被毛やフケを黄色培地に接種、培養。 1~2週間後、培地の赤色化と典型的な綿状の白色コロニーが形成される。 その後、顕微鏡検査にて菌の同定を実施する。 |
||

|

|
|
| 全身に皮膚糸状菌症がみられた高齢犬。四肢の境界明瞭な脱毛と色素沈着。 | ||

|

|
|
|
治療2か月後の発毛がみられた状態。 (残念ながら、3か月後再発がみとめられた。) |
||
毛包虫症(ニキビダニ症)
ニキビダニは、健康な犬の皮膚にも共生状態で少数の寄生がみとめられ、通常無症状である。しかし何らかの原因で共生関係が崩れると、毛包、皮脂腺などで過剰に増殖し、ニキビダニ症を発症する。ただし、その発症要因についてはいまだ十分な解明がなされていない。症状は脱毛、鱗屑、紅班、丘疹、膿皮症の併発などがみられ、重症例では潰瘍、びらんを呈することもある。
また、病変の範囲から局所性と全身性、発症年齢から若年性と成年性とに区別され、それざれ治療法、治療期間、予後に違いがみられる。

|

|

|

|

|